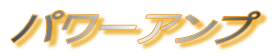
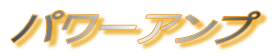
この価格としては18.5kgと重い方であり、デザインも大胆でゴージャス、メーターの照明も気品があり、ルックスだけでいうとA6に比べたらだいぶ貫禄が違い、A6の10万円は割高に見えてくる。内部は見るからに頼もしいもので、電源トランスはシールドケース入り、ケースのサイズは145×125×105㎜、電力容量345VA。フィルターコンデンサーは71V10000μF(35φ×80㎜)が4本。ヒートシンクはアルミダイキャスト。筆者の個人的見解としては、ヒートシンクはパワートランジスタの振動を押さえる働きがあり、重くて丈夫な方がよいと考えている。銅ブロック削りだしが理想だろうが、次善としてはアルミダイキャストだろう。
このアンプの特徴はLFB(リニア・フィード・バック)だ。簡単にいうと、前段にPFB(ポジティブ・フィードバック)をかけて、増幅度を無限大スレスレまで上げ、これを含む全回路に大量のNFBをかけるというもの。詳しい説明をしていると何ページにもなってしまうので全て省略するが、とにかく綱渡り的な回路テクニックで、歪みゼロ、ダンピング・ファクター無限大を実現しようというものである。ただし、アイデアとしては新しいものではなく管球アンプ時代には多くのアマチュアが挑戦して、失敗したり成功したりしていたものである。筆者もその体験があるので、初めは大丈夫かなと思ったが、そこは松下電産、あぶなっかしいものは売るわけがない。見事にコントロールして、安全なPFB-NFBを実現した。とはいっても、疑問はある。普通のNFBアンプでも、超高域は対象外ということで知らんぷりしているが、LFBのように大量のNFBをかけるアンプの超高域はどうなっているのだろうか。
さて、音の方だが、立ち上がりと立ち下がりにかなり特徴がある。音が直角に立ち上がり、直角に立ち下がる(消滅する)感じである。他のアンプだと、ズドーン、ドシーン、ガシャーン、と聴こえる音が、本機の場合、ズト、ドシ、ガシャと、瞬時に立ち上がって、瞬時に消えるのである。「1812年」の大砲も実に生々しい。これは凄いアンプが出てきたもんだと、最初はびっくり仰天していたが、ヒアリングを重ねているうちに疑問も出てきた。教会堂で録音した小編成のバロック・ミュージックのように、響きと雰囲気を最も大切にするようなソースでも、音が、パッと止まってしまうのである。やはり一長一短だなというのが結論。
しかし、このアンプの強烈なキャラクターをダイレクトに突きつけてくれたのは筆者宅のSPシステムだけであって、その後、いろいろヒアリングしてみた限りでは、このキャラクターはかなり弱められ、一般のアンプに比べて、ちょっと違うかな、という程度になっていた。このアンプのキャラクターをフルに発揮させるためには、ネットワークにLを一切使わないこと、重い振動系のウーファーを使わないこと、この2点が絶対条件と思う。
